「オーダーメイドで着物を仕立てたいけれど、完成までにどれくらい時間がかかるの?」
そんな不安を感じていませんか。
特に結婚式や成人式といった特別な日程に合わせる場合、仕立て期間がどのくらい必要かを正確に知ることはとても重要です。
納期の見通しが立たなければ、せっかくの晴れの日に着物が間に合わないという事態にもなりかねません。
この記事では、次のポイントをわかりやすく整理しています。
- オーダーメイド着物の仕立て期間と工程の流れ
- 追加加工(紋入れ・湯のし・裏地など)が納期に与える影響
- 短納期対応の可否と費用の関係
さらに、「採寸が遅れると仕立て開始が遅れること」や「繁忙期には通常よりも納期が延びる可能性」についても触れていきます。
この記事を読むことで、納期に焦ることなく安心してオーダーでき、予定通りに着物を受け取れるようになるでしょう。
Contents
オーダーメイド着物の仕立て期間とは何か―発注から完成までの全体の流れ

オーダーメイドで着物を仕立てる場合、「仕立て期間」とは単に縫製にかかる日数だけではありません。
反物の準備、採寸、加工、縫製、検品、仕上げまでの一連の流れを含みます。
そのため、同じ「オーダー」といっても選ぶ内容によって必要な時間は大きく変わります。
特に、成人式や結婚式など日程が決まっている場合は、工程の全体像を理解して逆算することが欠かせません。
ここでは、仕立てにかかる主な工程と、それぞれのステップが納期にどう影響するのかを整理していきます。
採寸・寸法確定のタイミングが納期に与える影響
仕立てを始める前に欠かせないのが「採寸」と「寸法の確定」です。
寸法が決まらなければ仕立てはスタートできません。
例えば、反物を持ち込みで注文する場合でも、体型に合わせた寸法表を工房や和裁士に渡すことが必要です。
この寸法確定が遅れると、縫製そのものは短期間で済んでも、全体の納期がずれてしまうことがあります。
特に注意したいのは、採寸の予約や日程が繁忙期に集中するケースです。
成人式前の秋から冬、春の卒業・入学シーズン前は採寸希望者が増えるため、早めに予定を立てることが大切です。
余裕を持って採寸を終えれば、縫製に取りかかる時点での遅延を防げます。
縫製方法(手縫い/ミシン/国内/海外)と通常の標準納期
仕立ての期間を左右する大きな要素が、縫製の方法と仕立て場所です。
- 国内手縫い:最も時間がかかりますが、丁寧な仕上がりが特徴。一般的に1か月前後が目安です。
- 国内ミシン縫い:一部の工程をミシンで行うため、手縫いより早く仕上がる場合があります。2〜3週間程度が目安。
- 海外仕立て:費用は抑えられるものの、輸送を含めるため納期はやや長めで、1.5〜2か月かかることもあります。
加えて、浴衣や木綿着物などシンプルな仕立ては比較的早く、フォーマルな留袖や振袖は工程が多いため時間を要します。
仕立て方の選択は、納期と費用のバランスをどうとるかによって決めるとよいでしょう。
追加加工が期間に与える要因―紋入れ・湯のし・裏地・特殊仕様など

オーダーメイド着物の仕立て期間は、縫製だけでなく「追加加工」の有無によっても大きく変わります。
反物の状態によっては、仕立てに入る前に整える工程が必要となる場合があります。
さらに、礼装用の着物では家紋を入れたり、裏地を付けたりといった工程が加わるため、通常納期よりも数週間長くなることがあります。
予定が決まっている場合は、これらの追加工程を考慮して逆算することが欠かせません。
ここでは代表的な加工と、それがどの程度納期に影響するのかを解説します。
紋入れ・湯のしなどのオプション加工にかかる期間の目安
フォーマルな着物では、背中や袖に家紋を入れる「紋入れ」が必要です。
この場合、染め抜き紋や刺繍紋などの種類によって納期が変わり、一般的には1〜3週間程度の追加が見込まれます。
また、多くの反物は仕立てに入る前に「湯のし」という加工を施します。
これは反物を蒸気で整え、生地の幅や風合いを安定させる工程で、1週間前後かかるのが一般的です。
湯のしを省略して仕立てに入ると、完成後に歪みやシワが出やすくなるため、基本的には必要な作業と考えた方が安心です。
季節・素材・裏地・派手さのある染めや柄あわせによる遅延要素
仕立て期間は、生地の種類やデザインの複雑さによっても変動します。
たとえば、単衣や浴衣のように裏地を付けない着物は仕立てが比較的早く進みますが、袷仕立てで胴裏や八掛を組み合わせる場合は、その分工程が増えます。
さらに、柄合わせが必要な訪問着や留袖などは、一つひとつの柄をきちんと合わせるために時間を要します。
素材の面でも違いがあり、絹や縮緬のような扱いに注意が必要な生地は、熟練の和裁士が丁寧に作業するため、通常より数日〜1週間ほど長くかかることがあります。
加えて、繁忙期には加工所や和裁所が混み合い、納期がさらに延びる可能性があるため、余裕を持った依頼が大切です。
急ぎの納期対応は可能か―特急仕立て・お急ぎ便などの選択肢
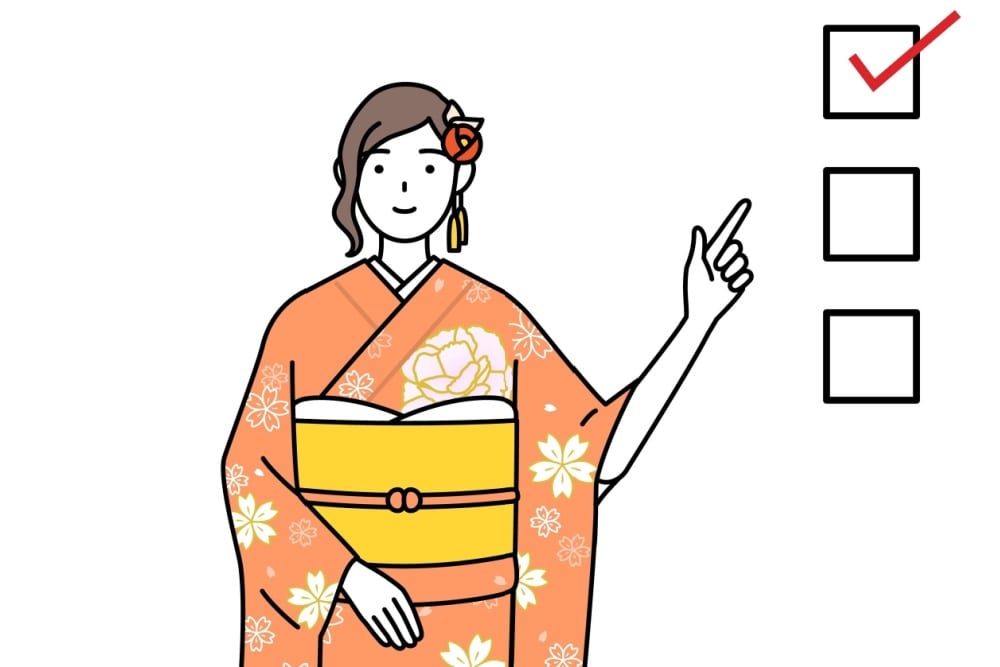
「予定日が迫っているのに、仕立てがまだ終わっていない」――そんな状況に対応するため、多くの仕立て店や和裁所では特急仕立てやお急ぎ便といったサービスを用意しています。
ただし、すべての依頼に対応できるわけではなく、反物の状態や加工の有無、繁忙期かどうかによっては受けられないケースもあります。
ここでは、急ぎの仕立てに関する選択肢と注意点を整理していきます。
特急対応の種類とその追加料金の相場
特急仕立てにはいくつかのパターンがあります。
最も一般的なのは「通常より優先して縫製に入る」タイプで、国内縫製なら通常30日程度かかるところを2〜3週間に短縮できる場合があります。
浴衣や木綿着物のように工程が少ないものなら、さらに早く仕上がるケースもあります。
その代わり、追加料金が発生するのが一般的です。
料金の目安としては、通常仕立て代に対して20〜30%程度上乗せされることが多いとされています。
さらに、急ぎでの加工(湯のし・紋入れなど)も依頼する場合は、それぞれの工程でも割増料金がかかることがあります。
急ぎ対応で注意すべきこと(妥協点・品質・検品など)
短納期の仕立てを依頼する場合には、いくつかの注意点があります。
まず、仕立て自体の工程を省略することはできないため、どうしても縫製者に大きな負担がかかります。
その結果、柄合わせや仕上げの細やかさに通常より差が出る可能性があります。
また、納期を優先するあまり検品やアイロン仕上げの時間が十分に取れない場合もあります。
急ぎ仕立てを依頼する際には、「仕上がりの品質に多少の妥協が必要な場合がある」ことを理解した上で依頼することが大切です。
どうしても妥協できない部分(柄合わせ・裄丈の正確さなど)がある場合は、必ず事前に伝えておきましょう。
発注時期とスケジュールの目安―結婚式・成人式など行事に間に合わせるために

着物の仕立ては、日程が決まっている行事に合わせて逆算するのが鉄則です。
特に成人式や結婚式など、延期や変更が難しいイベントでは、余裕を持ったスケジュールを立てることが欠かせません。
仕立て期間そのものは1〜2か月が目安ですが、繁忙期や追加加工の有無によってはさらに延びるため、最低でも数か月前からの準備が理想です。
ここでは行事別の発注時期の目安と、仕立て開始前にやっておきたい準備について解説します。
行事ごとの発注推奨時期(成人式・結婚式・入学式・祝賀会など)
- 成人式:1月開催が一般的なため、前年の夏頃までに反物や仕立ての相談を始めるのが安心です。秋以降は採寸や仕立て依頼が集中し、納期が遅れる可能性が高まります。
- 結婚式:参列や本人用いずれの場合も、式の3〜4か月前には発注しておきたいところです。家紋入れや裏地選びなど、フォーマル着物は加工が増えるため、余裕を見て動くことが重要です。
- 入学式・卒業式:3月や4月に行われるため、冬の繁忙期に重なります。前年の秋から相談を始め、12月頃までに発注しておくと安心です。
- 祝賀会やパーティー:日程が決まったらすぐに依頼するのがベスト。特に訪問着や留袖は柄合わせに時間を要するため、2〜3か月の余裕を見ておくと安全です。
発注~仕立て開始前に準備しておくこと(反物の選択・支払い・寸法・加工相談)
仕立て依頼をスムーズに進めるには、事前準備がとても大切です。まずは反物を用意し、素材や柄の特性を確認しておきましょう。
必要に応じて湯のしやガード加工などのオプションを決め、追加でどれくらい時間がかかるかも把握します。
次に採寸はできるだけ早い段階で行い、寸法表を確定させておくことが重要です。
寸法が決まらないと仕立てに入れないため、採寸が遅れるだけで全体の納期が後ろ倒しになります。
また、支払い方法や納品形式(自宅配送・店舗受け取りなど)も事前に確認しておくと安心です。
このように、反物の準備から採寸・加工相談までを前倒しで進めることで、仕立て工程がスムーズに流れ、納期に余裕を持つことができます。
費用との関係と納期を短くするための工夫

オーダーメイド着物の仕立てでは、納期と費用は密接に関わっています。
標準的な仕立てであれば数万円台から可能ですが、特急仕立てや特殊な加工を加えると、費用は一気に上がります。
特に「予定日に間に合わせたいから早くしてほしい」と依頼する場合、追加料金が発生するのが一般的です。
ここでは、費用に影響する主な要素と、納期を短縮しつつ予算を抑える工夫を紹介します。
費用に影響する要素(縫製方法・素材・裏地・加工・海外/国内など)
費用は大きく分けて「縫製方法」「素材や裏地」「加工の有無」によって変動します。
- 縫製方法:国内手縫いは技術料が高く、数万円以上かかることもあります。一方、海外仕立てやミシン併用は比較的安価ですが、納期が延びるケースもあるため要注意です。
- 素材や裏地:絹など高級素材は扱いが難しいため、仕立て代が上がりやすく、裏地の品質を上げればさらに費用は増えます。
- 加工の有無:湯のし、紋入れ、ガード加工などの追加工程は、それぞれ1〜3万円程度プラスになるのが一般的です。
- 仕立て場所:国内仕立ては安心感がある反面、海外仕立てより費用は高めです。
このように、仕立て方法やオプション選びが納期と費用に直結するため、優先順位を整理して依頼することが大切です。
予算を抑えつつ納期を短くするための工夫(セミオーダー・既製反物・納期オプション)
納期を短くしたいが、費用はなるべく抑えたい――そんなときは工夫次第でバランスを取ることができます。
まず、セミオーダー仕立てを選ぶ方法があります。
既存の寸法を基準に体型に近いサイズで仕立てるため、フルオーダーよりも時間が短縮でき、費用も抑えやすいのがメリットです。
次に、既製反物を選ぶ方法も有効です。
店舗が在庫として持っている反物であれば、湯のしや加工をすぐに行えるため、持ち込み反物より納期が早く進みます。
さらに、一部の仕立て店では「納期オプション」として追加料金を支払えば短納期に対応してくれる場合があります。
こうした工夫を取り入れることで、費用を抑えながらも日程に間に合わせる可能性を高められます。
重要なのは、どの要素を優先するかを明確にし、仕立て依頼の際に具体的に相談することです。
まとめ
オーダーメイド着物の仕立て期間は、縫製だけでなく採寸・加工・素材選びといった要素が重なり合って決まります。
標準的には1〜2か月程度が目安ですが、家紋入れや湯のしなどの追加工程や、繁忙期の混雑によってはさらに長くなることもあります。
反対に、特急仕立てや納期オプションを利用すれば短縮も可能ですが、その分費用が上がり、仕上がりに妥協点が出る場合もあります。
結婚式や成人式などの行事に合わせたい場合は、必ず日程から逆算して発注時期を決めることが大切です。
そのうえで、予算・納期・品質の優先順位を明確にし、仕立て依頼の際に具体的に相談することで安心につながります。
余裕を持ったスケジュールと適切な判断で、理想の着物をその日に間に合わせましょう。
着付師・着付講師。
一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。
美容師から転身し、24歳で教室を開講。
のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。
着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。
YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。
詳しく見る













この記事へのコメントはありません。