「長襦袢に腰紐を結ぶ正しい順序を知りたい!」
「長襦袢はどうやって着るの?」
「腰紐っていつ、どこで結べばいいの?」
着物の着付けに慣れていない方にとって、このような疑問はとても多いものです。
とくに初めて一人で着物を着ようとする方にとっては、順番や手の動かし方が分からず戸惑う場面もあるでしょう。
この記事では、こんなことが分かります。
- 長襦袢を着る際の正しい順番と衣紋の整え方
- 腰紐をどこに巻いて、どう結べば着崩れにくくなるか
- 腰紐の後に必要な整えと伊達締めの正しい使い方
さらに、これらの手順を加藤咲季さんのYouTube動画をもとに丁寧に解説し、着崩れしないための補正方法や腰紐の素材選びについても触れていきます。
正しい着付けは、ただ美しいだけでなく、自分自身が一日中快適に過ごすための大切な土台になります。
基本をしっかり押さえて、礼装やお出かけも安心して楽しめるようにしていきましょう。
Contents
長襦袢を正しく着る前の準備と衣紋の整え方
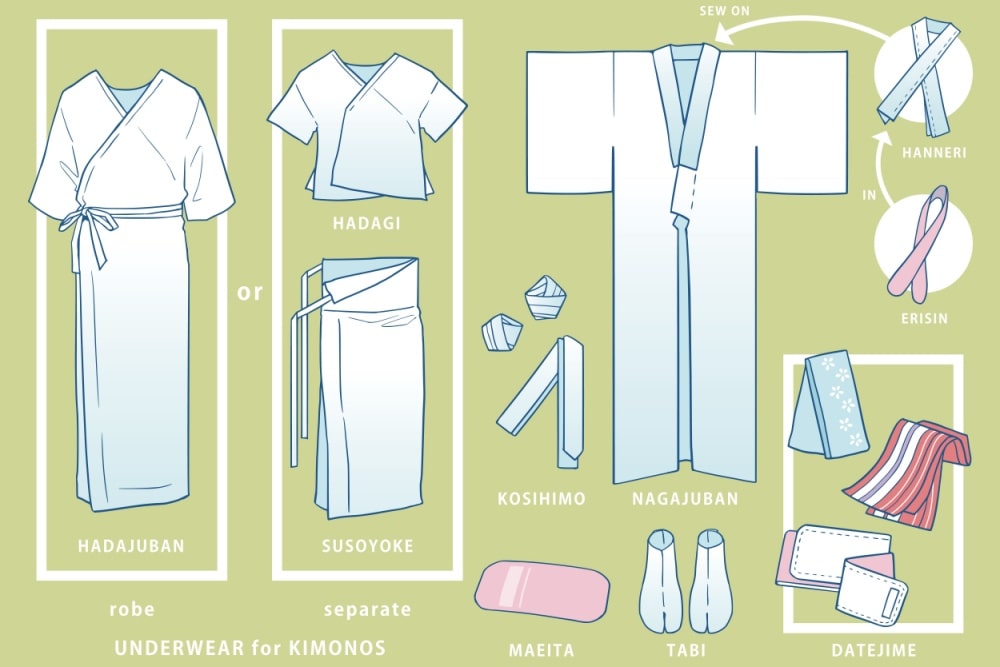
長襦袢を美しく着こなすためには、ただ羽織って腰紐を結ぶだけでは不十分です。
衣紋の抜き加減や衿元の形によって、着姿全体の印象が大きく変わるため、最初の準備と衿の合わせ方が重要なポイントになります。
とくに後ろ姿や首元の美しさは、他人の目に一番映る部分。だからこそ、正しい手順と意識が必要です。
この章では、長襦袢を着る前に確認しておくべき基本と、衣紋を美しく整えるためのコツを詳しくご紹介します。
加藤咲季さんの動画解説をもとに構成しており、着付け初心者の方でもすぐに実践できる内容です。
衣紋を抜く位置と効果
衣紋(えもん)とは、長襦袢や着物の後ろ襟部分の抜き加減のことを指します。
美しく衣紋を抜くことで、うなじがきれいに見え、着姿全体がすっきりとした印象になります。
加藤咲季さんは、衣紋を抜くときの基準として「拳1つ分」ほどの空間を目安にするとわかりやすいと解説しています。
この距離を保つことで、過剰に抜けすぎず、かつ詰まりすぎない絶妙なバランスを保てます。
重要なのは、衣紋を抜くときに“肩にしっかりと引くこと”。
加藤咲季さんの動画では、肩のあたりを両手で持ち、まっすぐ後ろへ引くことで自然な衣紋の抜きが完成すると説明されています。
また、この作業の前に「肩の位置をぐるっと回してからストンと落とす」ことで、襟が首にフィットしやすくなるともアドバイスしています。
衣紋がきれいに抜けていると、首が長く見え、姿勢もすっと整って見えます。
後ろ姿に自信が持てるようになるため、最初の一手としてぜひ丁寧に取り組んでください。
※参考動画:着物での綺麗じゃない立ち方
襟先の合わせ方と首回りの見せ方
襟元は着物姿の“顔”とも言えるほど重要なポイントです。
長襦袢の襟合わせが整っていないと、その上に着る着物の形も崩れてしまいます。
特に首回りの見せ方は、清潔感や品の良さを左右するため、丁寧な手順が必要です。
加藤咲季さんは動画内で、襟の合わせ方として「左右対称になるように丁寧に形を整える」ことを基本としつつ、「首にピタッと沿わせるように襟を寄せる」動作が重要であると解説しています。
襟が首から浮いてしまうと、たるみやシワの原因になるだけでなく、だらしなく見えてしまうため注意が必要です。
また、衿先の合わせ方にもコツがあります。
襦袢を羽織ったあと、左右の衿を交差させるときには「自分の鎖骨あたり」で交差させ、右手で左側の襟をしっかり押さえながら、左手で右側の襟をかぶせるようにすることで、左右の高さが揃いやすくなります。
このとき、顎下で“浅すぎず深すぎず”のV字になるよう意識しましょう。
咲季さんは、「着物の襟元は“衣紋+喉元の抜け”がセットで完成」とも話しています。
つまり、後ろ襟だけでなく、前の合わせも美しく見せることが一体感のある着姿につながるということです。
なお、衿合わせが崩れやすい場合は、補助として「コーリンベルト」などを活用するのもおすすめです。
加藤さんの別動画でも「苦しくないけれど緩まない襟元の作り方」として紹介されています。
※参考動画:着物での綺麗じゃない立ち方
腰紐を結ぶ正しい順序と位置を知る

長襦袢を整えたら、次に重要なのが腰紐の結び方です。
この工程を曖昧にしてしまうと、着崩れの原因になりやすく、一日中気になってしまうこともあります。
正しい順序と位置で腰紐を締めることで、長襦袢が体にしっかりフィットし、その後の着物も美しく仕上がります。
加藤咲季さんは、初心者にもわかりやすいように、腰紐を「押さえる・巻く・結ぶ・収める」の4ステップで丁寧に説明しています。
ここではその手順を、実践しやすい流れでご紹介します。
腰骨より少し上に巻く位置とクロスの仕方
腰紐はウエストではなく「腰骨より少し上のあたり」に位置させるのが基本です。
この高さで巻くことで、着崩れにくく安定した着姿を保つことができます。
ウエストに巻いてしまうと、動いたときに紐が下がってきてしまったり、襦袢の中でズレが起こりやすくなります。
加藤咲季さんの動画では、腰紐を体に当てたら、まず後ろでクロスして前に持ってきて、そのまま自然な力で締める流れが紹介されています。
ポイントは「締めすぎないこと」。
ギュッと引きすぎると苦しくなってしまい、呼吸がしづらくなるばかりか、襦袢が横に引っ張られてシワの原因にもなります。
また、体に沿わせる際に、腰紐の位置が左右で上下にずれないよう注意が必要です。
水平を意識して巻くことで、見た目にも整った印象になり、次に巻く伊達締めや着物との重なりも美しく仕上がります。
この巻き方は、特に「腰紐が緩んでしまう」「いつの間にか位置が下がっている」といった悩みを持つ方にとって、非常に効果的な方法です。
※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法
蝶結びから余りの処理までの結び方の流れ
腰紐を締めるときは、前で「蝶結び」にするのが基本です。
この形は見た目にもすっきりし、後の処理もしやすい利点があります。
ただし、蝶結びのまま放置すると、紐が帯や着物に響いたり、見えてしまうことがあるため、結んだあとは「必ず余りを中にしまう」ことが大切です。
加藤咲季さんは、蝶結びをした後、「左右の輪の部分を押し込み、結び目を内側に隠す」方法を推奨しています。
これにより、腰紐が表に出ることなく、着姿全体がすっきり見えるだけでなく、帯や伊達締めが当たったときの違和感も軽減できます。
また、腰紐が長すぎて余りが大きくなる場合は、「前に二重巻きにしてから蝶結びする」「余りを体に巻きつけてから隠す」などの応用テクニックも紹介されています。
初心者の方は無理に難しく考えず、まずは基本の蝶結びと余りの処理を丁寧に行うことが、着崩れ防止の第一歩になります。
加藤さんは「腰紐が見えると一気に着姿が雑に見える」とも強調しています。
だからこそ、結び目を隠す一手間が、美しい着付けにつながります。
※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法
腰紐を結んだ後に整える:おはしょりと伊達締めの連携

腰紐を正しく巻いたあとは、その上に長襦袢の布をきれいに整え、おはしょりを作っていきます。
この工程は、ただ布をたたむだけでなく、体に沿わせて「余分なシワを逃がす」作業でもあります。
また、仕上げに伊達締めを加えることで、襦袢全体が安定し、その上に重ねる着物も崩れにくくなります。
加藤咲季さんの解説では、「おはしょりの左右のバランスを取ること」「脇のたまりを逃すこと」が大切だとされています。
さらに、伊達締めの締め方にもコツがあり、「胴にフィットするけれど苦しくない」「着物と干渉しない」位置に整える必要があります。
ここでは、着崩れを防ぎ、見た目にも美しいおはしょりと伊達締めの連携方法を詳しくご紹介します。
おはしょりの整え方と布目を整える方法
おはしょりとは、長襦袢や着物の裾を腰紐で持ち上げた際にできる「折り返し部分」のことです。
これをきれいに整えることで、腰回りがすっきりと見え、着物姿全体が上品に仕上がります。
加藤咲季さんは、おはしょりを整える際、「まず左右の長さを揃えること」が第一条件としています。
そのうえで「脇に溜まっている布を後ろへ流す」ように整えるのがコツです。
動画内では、手のひらでそっと撫でるように整える動作を見せており、余計なシワを作らない自然な動きが印象的です。
脇に溜まる布(たもと)が多すぎると、着姿が膨らんで見え、動くたびにごわつきやズレの原因になります。
そこで、余った布を脇から後ろへ回してあげることで、見た目がすっきりし、腰回りも動きやすくなるのです。
さらに、左右の裾の高さにも注意が必要です。
おはしょりが片方だけ長いと、着姿が斜めに見えてしまうため、鏡を見ながら両側の折り返しが同じ高さになるよう確認しましょう。
この整えの工程は地味に見えますが、着姿の“完成度”を決定づける非常に重要な作業です。
※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法
伊達締めの位置と締め方・締め面の広さの意識
伊達締めは、長襦袢や着物を安定させるための補助帯です。
腰紐の上から巻くことで、襦袢の襟元やおはしょりをしっかりと固定し、着崩れを防ぐ役割を果たします。
咲季さんの動画では、「締める強さ」「面の広さ」「巻く高さ」の3点に注意するようアドバイスされています。
まず位置は、「腰紐のすぐ上あたり」、つまりウエストのやや下に巻くのが基本です。
高すぎると苦しくなり、低すぎると襦袢の襟が動きやすくなってしまいます。
腰紐のラインに沿うように自然に巻くことで、体にしっかりフィットし、余計な力をかけずに安定します。
締め方については、しっかりと固定することが大切ですが、力任せに締めすぎるのはNGです。
咲季さんは「息を吸って、吐いたときに締めるくらいがちょうどよい」と説明しており、体がリラックスしたタイミングで巻くことで一日中快適に過ごせるようになります。
伊達締めは素材によっても着心地が変わります。
ゴム入りのものは初心者に扱いやすく、広幅タイプは襟元の浮きやすい方におすすめです。
咲季さんは、「面積が広くなるほどズレにくくなる」という点も解説しています。
美しい着姿は、腰紐と伊達締めのWサポートによって生まれます。
これらを適切に扱うことが、安定した着付けへの大きな一歩になります。
※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法
着崩れしない着付けのポイントと補足知識

着付けは手順どおりに進めるだけでは不十分です。
一見整っているようでも、時間が経つと襟が緩んできたり、おはしょりがずれてきたりと、さまざまな“着崩れ”のリスクがあります。
とくに長襦袢と腰紐まわりは、動作のたびに緩みやすい部分だからこそ、あらかじめ崩れにくくする工夫が必要です。
加藤咲季さんは、「きれいに着付けること」と「一日中その状態をキープすること」は別の技術であると話しています。
この章では、実際に咲季さんが解説している着崩れ防止のための調整ポイントや、腰紐の素材・長さによる違いなど、知っておくと安心な補足情報を紹介します。
背縫い・肩・脇のシワを取る整え方
着付けを終えた直後に見落としがちなのが、「背中」と「脇」のシワです。
特に背縫いのラインが歪んでいると、後ろ姿がだらしなく見えてしまいます。
加藤咲季さんは、「背中から肩、脇へと手で撫でる動作」を習慣にすることで、見違えるほど着姿が変わると話しています。
具体的には、襦袢を腰紐で固定した後、背中中央の“背縫い”部分を軽く引き下げ、シワを後方へ流すように両手で撫でます。
左右の肩先にも布がたまりやすいので、肩から脇に向かって、優しく布を流すように整えるのがコツです。
さらに、脇部分は特に“動きによってもたつきやすい”箇所。
布が余っていると腕の可動域を邪魔し、見た目にも横に膨張して見えてしまいます。
脇下の布を背中方向へ寄せ、体に沿わせるようにするだけで、細くすっきりとした印象になります。
咲季さんは「シワ取りは着物を着る前の“下ごしらえ”」と位置づけており、この段階での整えが仕上がり全体を大きく左右することを強調しています。
※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法
腰紐の素材・長さ・代用品の選び方
腰紐と一口に言っても、実は素材や長さによって使い勝手が大きく異なります。
加藤咲季さんは「初心者には扱いやすい腰紐を選ぶことが、きれいに着るための第一歩」と話しています。
おすすめの素材は「モスリン」や「綿混紐」。
柔らかくて締めやすく、滑りにくいのが特徴です。
ポリエステル製などのつるつるした腰紐は、慣れないうちは結び目が緩んだりほどけやすくなったりするため、初心者には不向きです。
長さの目安は「240cm前後」が基本。体格に合わせて調整する必要はありますが、短すぎると蝶結びがしづらくなり、余りを処理できないことがあります。
逆に長すぎる場合は、体に巻きつけて隠す処理が必要です。
また、咲季さんは補正タオルやフェイスタオルを「腰紐代わりに使う応急処置」も紹介しています。
たとえば旅先やイベント会場など、腰紐を忘れた際にはタオルを細長く畳んで代用し、仮留めに活用することも可能です。
腰紐は「単なる紐」ではなく、着姿全体の土台を支える重要な道具です。
素材・長さ・使い方をきちんと理解しておくことで、着付けの安定性が格段に上がります。
まとめ
長襦袢と腰紐の着付けは、着物姿の美しさと快適さを左右する重要な工程です。
ただ順序どおりに進めるだけでなく、それぞれの動作に意味があり、着姿全体の完成度を高めるための工夫が込められています。
今回ご紹介した手順は、加藤咲季さんのYouTube動画に基づいたものです。
特にポイントとなるのは以下の4点です。
- 衣紋は“拳ひとつ分”を目安に美しく抜く
- 腰紐は「腰骨より少し上」で水平に巻く
- 蝶結びのあとは結び目を中に収め、すっきりと仕上げる
- 伊達締めは締めすぎず、襟元を固定するために活用する
また、着崩れを防ぐためには、背中や脇のシワ取り・おはしょりのバランス調整といった“整えの時間”も欠かせません。
腰紐の素材選び一つとっても、着付けの安定感に大きく影響することを忘れずに。
初めての方は一度で完璧に仕上げるのは難しいかもしれません。
しかし、ポイントを押さえて手順に沿って進めれば、誰でも着姿の美しさを引き出すことができます。
ぜひ、この記事を参考にしながら、動画と一緒に練習してみてください。
自分自身で着物を着る楽しさと達成感を、少しずつ実感していただけるはずです。
着付師・着付講師。
一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。
美容師から転身し、24歳で教室を開講。
のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。
着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。
YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。
詳しく見る








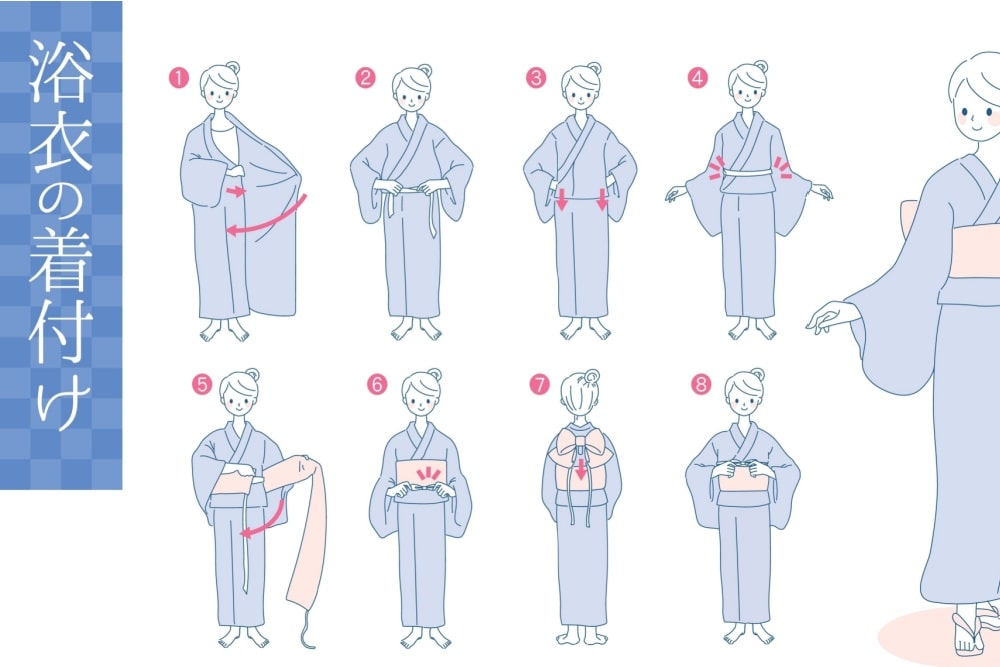



この記事へのコメントはありません。