「成人式や卒業式で振袖を着る予定だけど、小物が多すぎて何を準備すればいいのか不安…」と感じていませんか?
着物は普段の洋服と違い、腰紐や帯板など細かな小物が必要不可欠です。
当日サロンに持参する荷物が不足していると、最悪の場合は着られないこともあるため、事前のチェックが欠かせません。
特に初めての方や、準備を任される保護者の方にとっては「何が必須で、何が代用できるのか」を明確にしておくことが安心につながります。この記事では次のポイントを整理しました。
- 振袖・訪問着の着付けに必要な小物リスト
- 着付けサロンや式場に持参すべきアイテムと注意点
- 忘れがちな小物や代用品の選び方
この記事をチェックリスト代わりに準備を進めれば、当日慌てることなく安心して着物姿を楽しめます。
Contents
振袖・訪問着の着付けに必要な小物チェックリスト
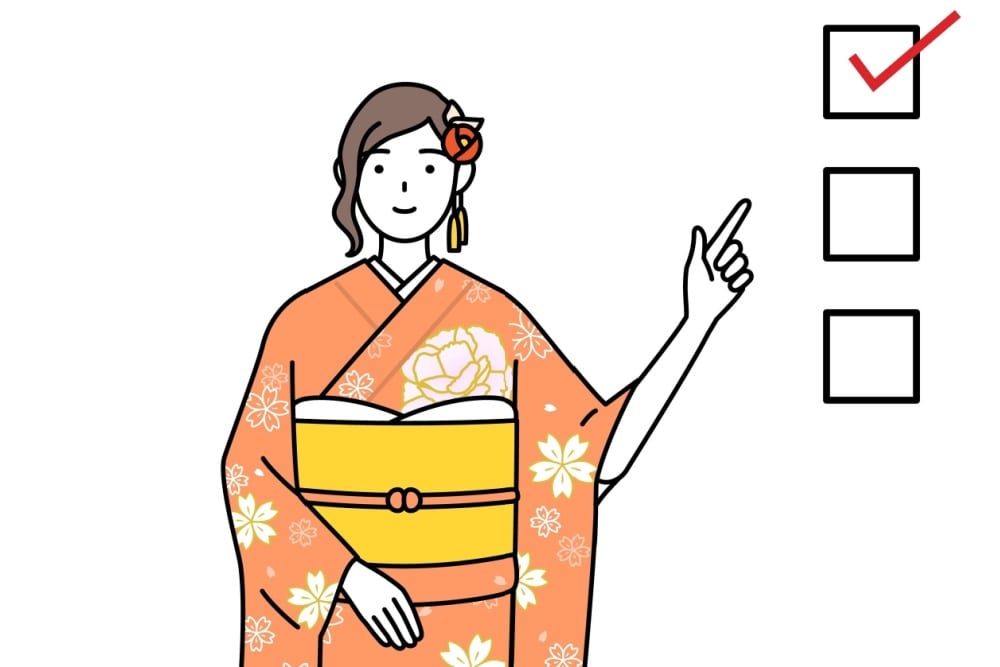
成人式や卒業式などの着付けでは、和装小物が一つでも欠けると仕上がりに大きく影響します。
特に初心者は「名前は聞いたことがあるけれど、どんな役割なのか分からない」という小物も多いものです。
ここでは、振袖や訪問着を着る際に最低限そろえるべき小物を、カテゴリごとに整理しました。
事前に確認しておくことで、当日の着付けがスムーズに進みます。
肌着・補正アイテム(和装ブラ・肌着・裾よけ・タオルなど)
着物を美しく着るためには、まず下地作りが欠かせません。
洋装用の下着では胸の形や体の凹凸が強調されすぎて、帯や襟元が整いにくくなります。
そのため、和装ブラやスポーツブラなど、胸を平らに近づけるタイプが適しています。
また、直接着物に汗や皮脂が移らないように肌着や裾よけを着用し、補正用に薄手のタオルを数枚用意して体のラインを整えるのが基本です。
加藤咲季さんも動画内で、和装ブラやワンピース型の肌着、セパレート型の肌着の違いを詳しく解説しています(※)。
キャミソールタイプは脇が見えやすいため避け、半袖タイプを選ぶと安心です。
特に夏場は通気性のよい素材を取り入れるなど、季節に合わせた工夫もポイントになります。
※参考動画:肌着の種類
着付けの基本小物(腰紐・伊達締め・帯板・帯枕など)
次に必要なのが、着物を固定し、形を保つための基本小物です。
腰紐は着物や長襦袢を留めるために最低4本以上、伊達締めは襟元を整えるために2本あると安心です。
帯板は帯のシワを防ぎ、前姿を美しく見せる役割を担います。
帯枕はお太鼓結びや振袖の変わり結びに欠かせない道具で、仕上がりに大きく影響します。
これらは全て「目には見えにくいけれど欠かせない小物」です。
忘れてしまうと着崩れや見た目の乱れにつながるため、事前の確認が必須です。
特に腰紐と伊達締めは素材によって滑りやすさや締め心地が異なるので、初めての方は柔らかめで扱いやすいものを選ぶと安心です。
帯まわりの小物(帯揚げ・帯締め・衿芯など)
帯まわりを美しく仕上げるために必要なのが、帯揚げ・帯締め・衿芯などの小物です。
帯揚げは帯枕を隠しながら装飾としての華やかさを加え、帯締めは帯の中央をしっかりと固定し全体を引き締めます。
衿芯は長襦袢の半襟に差し込んで襟元をパリッと整えるために必須のアイテムです。
加藤咲季さんの動画【帯揚げの使える色、使えない色とは?】では、初心者が揃えるべき帯揚げの色について解説されています。
淡いピンクやグレーなどは幅広いコーディネートに対応できるため、最初の一枚としておすすめです。
帯揚げや帯締めはコーディネートの印象を左右するため、シンプルかつ汎用性の高い色を優先すると安心です。
当日サロンや式場に持参するものリスト

着付けを依頼する場合、サロンや美容院によっては基本の小物を用意してくれるところもあります。
しかし多くの場合、必要な小物一式は利用者側が持参するのが前提です。
当日忘れ物をすると着付けが進まず、せっかくの式典に支障が出てしまいます。
ここでは「必ず持参するもの」と「あると便利なもの」に分けて整理しました。
前日のうちにバッグや風呂敷にまとめておくと安心です。
必ず持参するもの(着物・帯・長襦袢・小物一式)
まず欠かせないのは、着物・袋帯・長襦袢といった大物一式です。
これに加えて、腰紐・伊達締め・帯板・帯枕・帯揚げ・帯締め・衿芯などの基本小物を必ず揃えておきましょう。
長襦袢には半襟を縫い付けておく必要があるため、事前に確認しておくことも大切です。
加藤咲季さんの動画でも解説されているように、最低限そろえるべきものはこのセットです(※)。
特に振袖は帯結びが華やかで小物の使用数も多く、帯枕や帯板を忘れると仕上がりが大きく崩れてしまいます。
まずは「なくてはならない物」を漏れなく準備しましょう。
※参考動画:着物でのお出かけに必要なものとは?
当日便利な持ち物(草履バッグセット・足袋・ハンカチ・化粧ポーチなど)
必須小物に加えて、当日の快適さを支える持ち物も重要です。
足元を整える足袋、フォーマルに合わせた草履バッグセットは必ず準備しましょう。
バッグはショルダー型ではなく、手に持てるハンドバッグが適しています。
さらに、ハンカチやティッシュ、化粧直し用のポーチも忘れずに。
加藤咲季さんの動画【着物の時の履物について語ります】では、初心者にはクッション性のある草履や鼻緒が太めのものが歩きやすくおすすめとされています。
また【着物でのお出かけに必要なものとは?】では、応急処置用に「クリップ」と「腰紐1本」があると安心と解説されています。
荷物は最小限にしつつ、忘れると困る小物を入れておくことで、式典中も安心して過ごせます。
忘れがちな小物と代用品の選び方

着付けで必要な小物は数が多いため、準備の段階で抜け漏れが起きやすいものです。
特に普段は目にする機会が少ないアイテムほど、当日になって慌ててしまうことがあります。
ここでは「うっかり忘れがちな小物」と「代用品で対応できるもの」をまとめました。
余裕を持って揃えておくことで、当日の不安を大きく減らせます。
忘れやすい定番アイテム(衿芯・腰紐の本数・補正用タオルなど)
チェックリストに入れていても、意外と準備を忘れやすいのが衿芯です。
長襦袢に差し込むだけの小物ですが、これがないと襟元がくたっとしてしまい、着姿全体が崩れて見えます。
また、腰紐の本数も要注意です。
最低4本とされていますが、振袖の場合は補助的に5〜6本使うこともあります。
さらに、補正用のタオルも忘れがちなアイテムの一つです。
加藤咲季さんの動画では、体型に合わせてタオルを使うことで、着崩れや紐のずれを防げると解説されています(※)。
タオルは新品よりも柔らかく洗濯済みのものを選ぶと扱いやすく、補正しやすくなります。
※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法
代用品で対応できる小物(スポーツブラや洋装インナー、手ぬぐいなど)
必ずしも和装専用でなくても代用できる小物もあります。
たとえば、和装ブラが手元にない場合はスポーツブラで代用可能です。
ただし、ワイヤー入りのブラジャーは痛みや着崩れの原因になるため避けましょう。
また、肌着は和装用のワンピース型やセパレート型が理想ですが、半袖タイプの洋装インナーでも対応できます。
補正用のタオルの代わりに、手ぬぐいや薄手のハンドタオルを使うことも可能です。
加藤咲季さんの動画でも紹介されているように、夏場はユニクロのエアリズムなどを活用する方法もあります(※)。
必須小物をすべて新品でそろえるのは大変ですが、代用品を工夫することで負担を減らしつつ、しっかりと着姿を整えることができます。
※参考動画:肌着の種類
履物・バッグ選びの注意点

着物姿を引き立てるためには、足元やバッグの選び方も重要です。
振袖や訪問着は格の高い装いのため、カジュアルな履物や普段使いのバッグではバランスが崩れてしまいます。
さらに、選び方を誤ると「歩きにくい」「着崩れしやすい」といったトラブルの原因にもなります。
ここでは、初心者が安心して選べる履物とバッグのポイントを整理しました。
草履と下駄の違いと初心者向けおすすめ
振袖や訪問着といったフォーマルシーンには、基本的に草履を合わせるのが正解です。
下駄はカジュアルな着物に向いており、式典などの場には適しません。
草履は台の高さや鼻緒の太さによって履き心地が大きく変わります。
初心者にはクッション性があり、鼻緒が太めの草履が足に優しく、長時間の式典でも疲れにくいのが特徴です。
加藤咲季さんの動画でも、初心者向けの草履選びのポイントとして「クッションが効いていること」「鼻緒が太めであること」が紹介されています(※)。
慣れていない方は硬い台や細い鼻緒の草履を避け、歩きやすさを優先して選ぶと安心です。
※参考動画:着物の時の履物について語ります
着物に合うバッグと避けたい形
バッグは、着物全体の雰囲気に合わせたフォーマル仕様を選びましょう。
振袖や訪問着には、草履とセットになったフォーマルバッグが定番です。
小ぶりなハンドバッグやクラッチ型であれば、装いの格を損なうことなく華やかさを演出できます。
一方でショルダーバッグは避けるべきアイテムです。
肩にかけると襟元が崩れやすく、生地も摩擦で傷みやすくなります。
加藤咲季さんも動画内で「ショルダーバッグはおすすめしない」と解説されており、実際に帯や襟を崩してしまう原因になります(※)。
必要な荷物が入る大きさを選びつつ、手に持てるタイプで揃えるのが安心です。
※参考動画:着物でのお出かけに必要なものとは?
小物の色選びとコーディネートの基本

着物の印象を大きく左右するのが、小物の色選びです。
帯揚げや帯締めといった小物は、単なる実用アイテムではなく、全体の雰囲気を整えるアクセントになります。
色の選び方を誤ると、せっかくの着物姿がちぐはぐに見えてしまうため、初心者こそ「合わせやすい色」からそろえることが大切です。
ここでは、汎用性の高い色と避けた方がよい色の傾向をまとめました。
使いやすい帯揚げ・帯締めの色
最初にそろえるなら、淡い色調の小物がおすすめです。
たとえば、薄いピンクやグレー、生成りに近いオフホワイトなどは、幅広い着物や帯に合わせやすく、フォーマルからセミフォーマルまで活用できます。
特にグレーや生成りは「無難だけれど上品」な印象を与えるため、成人式や結婚式などでも安心です。
加藤咲季さんも動画にて「薄いピンクやグレーは使い回しが効き、万能に近い」と解説しています(※)。
まずは1〜2色のベーシックな小物を揃えることで、後々の着回しも楽になります。
※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?
避けた方がよい色・組み合わせ
反対に、鮮やかすぎる色や中途半端な色味は初心者には扱いづらい傾向があります。
ショッキングピンクやビビッドなブルーはアンティーク着物に映える一方で、現代のフォーマルな振袖や訪問着では浮いてしまう場合があります。
また、くすんだピンクや曖昧な色合いは、コーディネート全体をぼんやりと見せてしまうため注意が必要です。
動画【帯揚げの使える色、使えない色とは?】でも「中途半端な色は合わせにくい」と指摘されています。
どうしても濃い色を取り入れたい場合は、帯締めや髪飾りなど小物の一部でアクセントとして使うのが安全です。
まとめ
着付けに必要な小物は多く、一つでも欠けると当日の準備に大きな支障をきたします。
肌着や補正用タオルなどの下準備アイテムから、腰紐や伊達締めといった基本小物、さらに帯揚げや帯締めなどの装飾小物まで、全てが揃って初めて美しい着姿が完成します。
また、当日は草履やバッグなどの持ち物も忘れずに準備し、ショルダーバッグのように着崩れにつながるものは避けるのが安心です。
小物の選び方や色の組み合わせ次第で印象が大きく変わるため、初心者はまず「合わせやすい基本色」からそろえると失敗しません。
この記事をチェックリスト代わりにすれば、成人式や卒業式、結婚式といった特別な日も安心して迎えられます。
前日までに荷物をひとまとめにして、忘れ物のない状態で晴れの日を楽しんでください。
着付師・着付講師。
一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。
美容師から転身し、24歳で教室を開講。
のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。
着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。
YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。
詳しく見る












この記事へのコメントはありません。