「衿芯って、どこにどうやって入れたらいいの?」
「凸凹のあるカーブ型って、どっちを上にすればいいの?」
「ちゃんと入れたはずなのに、なんだか衿元がきれいに決まらない…」
着物の着姿を整える上で、衿芯の扱いに悩んでいませんか?
とくに初心者〜中級者の方にとっては、正しい位置や向きがわかりづらく、せっかく頑張っても「なんとなく不自然」に見えてしまうこともあります。
この記事では、以下のようなポイントを中心に、衿芯の正しい扱い方を解説していきます。
- 衿芯の差し込み位置と基本的な手順
- 凸型・凹型カーブ芯の選び方と着姿の違い
- 衿芯がスムーズに入る半衿と襦袢の準備のコツ
さらに、着付け師・加藤咲季さんのアドバイスも随所に交えてご紹介します。
着姿をもっと美しく整えたい方は、この記事を読み進めることで、衿芯に関する迷いが解消され、より自然で洗練された印象に近づけます。
Contents
衿芯はどこにどう入れる?基本の挿し方と正しい位置
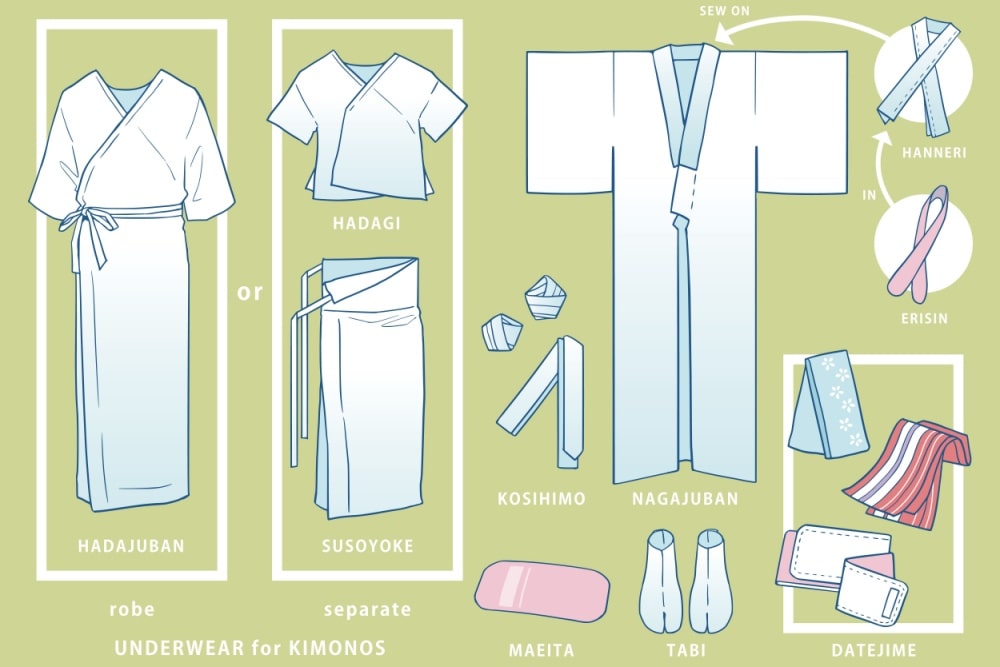
衿芯の入れ方ひとつで、衿元の立ち上がりや衣紋の抜け感が大きく変わります。
特に初心者のうちは、「何となく差し込んでいるだけ」になりがちですが、実は正しい差し込み位置や方向を守ることが、着姿の美しさを支える基本です。
ここでは、最も一般的で失敗の少ない衿芯の入れ方を、ステップごとに整理して解説します。
半衿と地襟の間に体側から差し込む理由
衿芯を差し込む際の基本は、「体側(内側)から、半衿と地襟の間に通す」ことです。
衿芯は、半衿と襦袢の間の“袋状”の部分に収めることで、自然なカーブとハリを出すことができます。
加藤咲季さんも「衿芯は、後ろ中心から左右に向かって通す」「途中でねじれないよう注意」とアドバイスしています。
また、後ろから前へ向けて差し込むことで、左右の長さを均等に保ちやすく、背中側の中心(背縫い)と衿芯の中央を合わせやすくなるメリットもあります。
このように、衿芯を“内側から半衿の中に収める”という手順は、衿芯の役割を最大限に活かす上で非常に大切です。
背中心で左右対称に位置を整える方法
衿芯は、「左右の長さと位置を均等にする」ことが基本です。
その目印となるのが、襦袢の背縫い(背中心)です。
衿芯を通す際は、まず後ろ中心に芯の中央を合わせ、そこから左右にゆっくりと均等に差し込んでいきましょう。
このとき、片側だけが長くなったり、片方が深く入りすぎたりすると、衿山がズレて着姿全体が不自然に見えてしまいます。
加藤咲季さんは「左右対称になっているかを手でなぞって確認しながら差し込むと、きれいに整う」とアドバイスしています。
また、差し込みすぎると衿が立ちすぎてしまい、逆に浅いとハリが出ず、だらしなく見えるため、「程よい位置まで差し込む」こともポイントです。
理想は、肩線よりやや手前あたりで止めること。肩まで芯が届くと、肩周りが不自然に浮く原因となります。
カーブ型襟芯の向きの選び方|凸?凹?着姿との関係

カーブ型の衿芯は、首元に自然な丸みを与えたり、衣紋の抜けを美しく見せたりするために設計された便利なアイテムです。
しかし、形状の「凸凹」どちらを上にするのかは迷いやすいポイント。
正解は一つではなく、体型や好みによって使い分けることができます。
ここでは、各形状の効果と、どう使い分ければよいかを丁寧に解説します。
凸型を衿山に入れた場合の印象と衣紋の角度
カーブの「凸」部分を衿山(外側)に向けて入れると、首の後ろに沿ってゆるやかな丸みが生まれます。
この方法は、衣紋をやや浅めに抜きたい方、または首が細めで直線的に見えやすい方におすすめです。
凸側が外に向くことで、衿に自然な張りと高さが出て、柔らかい印象の衿元になります。
また、衣紋がピンと張らず、自然にカーブを描くため、「詰まりすぎず、抜けすぎない」程よい襟元を目指す人にも向いています。
加藤咲季さんも「凸型を外にして使うと、衣紋の丸みが優しく出る」と解説しており、初心者にも扱いやすい方法といえます。
凹型を衿山に入れた場合の首元の見え方と選び方
一方で、カーブの「凹」部分を衿山(外側)に向けると、衣紋の抜けが深く、シャープな印象に仕上がります。
これは、衣紋を大きく抜きたい場合や、首が短めで衿元にゆとりが欲しい方におすすめの入れ方です。
凹型を使うと、衿芯が襦袢に密着しすぎず、少し外に広がる構造になるため、後ろ姿に“抜け感”を強調できます。
ただし、首が細い方が使うと、衿元が浮きすぎる印象になりやすいので、好みや体型に応じて選ぶことが大切です。
加藤咲季さんも、「衣紋の形をコントロールしたいときは、衿芯の向きを変えて試してみるのがおすすめ」と述べています。
まずはどちらも試して、自分の顔まわりや後ろ姿にしっくりくる方を選ぶのが最も確実です。
半衿と襦袢の準備も重要|衿芯との連携ステップ

衿芯を正しく入れるためには、前提として「半衿と襦袢が適切に準備されていること」が欠かせません。
とくに初心者の方にとっては、半衿の縫い付け方や下準備がうまくいっていないことで、衿芯がうまく差し込めなかったり、衿山がガタついたりする原因になります。
ここでは、衿芯がスムーズに入り、美しいラインを作るための事前準備について解説します。
半衿の縫い付け手順とテンション調整のコツ
半衿を襦袢に縫い付ける際の基本は、「ピンと張りすぎず、たるませすぎず」の絶妙なテンション感です。
張りすぎると衿芯が入らなくなり、逆に緩すぎると衿山が崩れてしまいます。
加藤咲季さんの動画では、手順として以下のように説明されています。
- 長襦袢の衿部分(地衿)に半衿を沿わせて、中心(背縫い)を合わせる
- 縫い始める前に仮止め(しつけ)で全体のバランスを確認する
- 細かく並縫いをすることで、厚みの偏りやよれを防ぐ
特に「半衿の縫い目は、表に響かない位置に細かく縫う」「襟芯が通ることを前提に、通し口を残しておく」といった細かいポイントも重要です。
参考動画:長襦袢の半衿のつけ方(衿芯の通し方あり) ※現在非公開
簡単に仕上げる裏技(両面テープ・ファスナー式など)
「縫い付けるのは苦手」「とにかく手早く仕上げたい」という方向けに、市販されている便利グッズも存在します。
代表的なものが、半衿用の両面テープや、ファスナー式の半衿カバーなどです。
ただし、加藤咲季さんの動画では「両面テープは一部の半衿(レース・刺繍入り・高級品)には不向き」との注意点もあり、選び方には慎重さが必要です(※)。
具体的には、テープをはがす際に生地が傷みやすく、表面が毛羽立つリスクがあるためです。
一方で、てぬぐい素材のように丈夫な半衿や、普段着用の襦袢に使う分には便利で時短にもなるため、TPOに応じた使い分けがポイントです。
※参考動画:テープで貼ってはいけない半衿3選
まとめ
衿芯は「正しく入れる」だけで、衿元の印象が大きく変わります。
内側から半衿と地襟の間に通し、背中心で左右対称に整えることが基本。
カーブ型を使う場合は、凸型・凹型それぞれの特徴を理解し、自分の体型や衣紋の抜き具合に合わせて選ぶことが重要です。
さらに、衿芯をスムーズに差し込むためには、半衿と襦袢の事前準備が欠かせません。
縫い付ける際のテンションや、通し口の工夫など、細やかな手仕事が最終的な着姿の美しさに直結します。
衿芯の扱いに自信がつけば、衿元が自然と整い、着姿全体がぐっと美しく仕上がります。
着物を着る楽しさもより深まるはずです。ぜひ、日々の練習に活かしてみてください。
着付師・着付講師。
一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。
美容師から転身し、24歳で教室を開講。
のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。
着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。
YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。
詳しく見る













この記事へのコメントはありません。